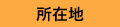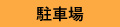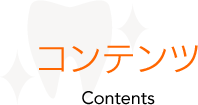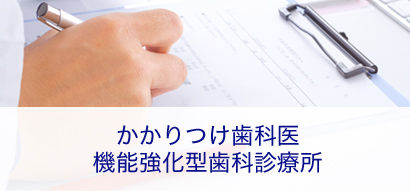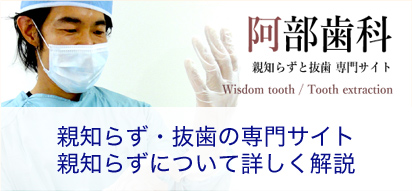本院長ブログでは、専門の歯科医の視点で歯科治療に関する新たな内容や、多くの方に役立つような
歯の豆知識、お口や歯のケアに関する話題などを定期的に掲載しています。
本日は多くの患者さんが気になる「歯並び」に関する内容を詳しく解説いたします。
噛み合わせを語るに当たりまして、まず考えておかなければならないことがあります。
歯科大学での補綴の授業では当たり前のようにやる内容ではありますが、
一般の方は普通は知らない内容についてを少し専門的となりますが、お話ししたいと思います。
記事更新日:2025年5月13日
モンソンの球面説とは?
モンソン博士という人がその昔に提唱した理論になるのです。それは、上顎や下顎のすべての
歯のそれぞれの山が篩骨鶏冠の近くを中心にしまして直径8インチの球面に接するという
内容です。
噛む上で歯が並んでいる位置におきまして、この「球面上に歯が並んでいることが
咀嚼するための動きとして大切である」とされています。
歯はいろんな角度から合わさることによって食べ物を噛み切ったり、
すりつぶしたりすることになるのです。
人間の顎は色んな動きをするのです。ワンちゃんでは食べ物を食べる時には
口を開閉するような動きしかできないのです。
ですが、私たち人間は顎を少し横に動かしたりすることができ、噛みきったり
すりつぶしたりすることが可能です。
スピーの彎曲、ウィルソンの彎曲について
このモンソンの球面は「横側から見た歯の並びの彎曲をスピーの彎曲」と言われるのであります。
正面から見た歯の並びの彎曲をウィルソンの彎曲と言われます。
補綴の研究では、過去の様々な研究者たちがその噛み合わせや歯の並びに対して理論的な根拠、
いわゆるエビデンスを見つけようとして頑張っていました。
そして、そのお陰で理論を基にした現在の臨床が成り立っています。
その事が噛み合わせにおいて、何を意味するか
これらのことが何を意味しているか?と考えますと、スムーズなこの球面が噛み合わせの安定を
保つことになっているということになります。
噛み合わせが安定することによって、顎関節が安定した位置になるということになります。
そして、これは噛み合わせの安定が顎関節症を引き起こさないようになるとも
考えられるのではないでしょうか。

噛み合わせの安定は“日々の生活の豊かさを与えるのにも大切なこと”ではないでしょうか。
噛み合わせのストレスをなくすことは、満足した食べる楽しみに寄与することになると
考えます。
私も含め、多くの歯科医は多くの噛み合わせに関する理論を勉強し、患者さんのお口の悩みを
解決していきたいと思っています。
歯並び/噛み合わせでお困りなら
当院では歯やお口のお悩み以外にも歯並びに関連するお悩みや、噛み合わせの不具合に伴う
トラブルについて、ご相談に応じています。
患者様への細かなヒアリングと検査により 適切に改善と歯科治療ができますよう、
努めています。「長く噛み合わせで困っている…」といった方は一度ご相談下さい。
丁寧なコミュニケーションと治療で、多くの患者様にご満足をいただいております。
【記事の執筆者】
千種区の歯医者 阿部歯科院長 阿部 丈洋(あべ たけひろ)
≪院長の主な経歴≫

| 1978年: | 名古屋市千種区生まれ |
| 1997年: | 名古屋 東海高校 卒業 |
| 2003年: | 奥羽大学 卒業 |
| 2003年: | 愛知学院大学歯学部研修医、稲沢市民病院勤務 |
| 2004年: | 愛知学院大学第2口腔外科 勤務 |
| 2005年: | 岐阜県立多治見病院 救命救急、麻酔科レジデント |
| 2006年: | 愛知県済生会病院 歯科口腔外科 医員 |
| 2009年: | 加藤歯科 勤務 |
| 2016年: | オカダ歯科クリニック 勤務 |
| 2018年: | 千種区の阿部歯科 院長就に就任 |




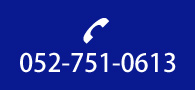



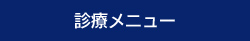
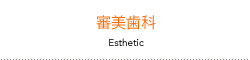

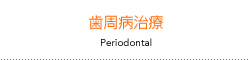


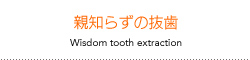





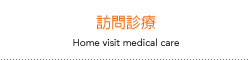






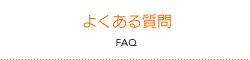




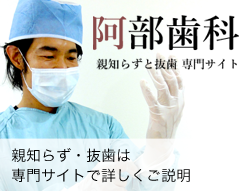


 千種区の痛くない歯医者
千種区の痛くない歯医者